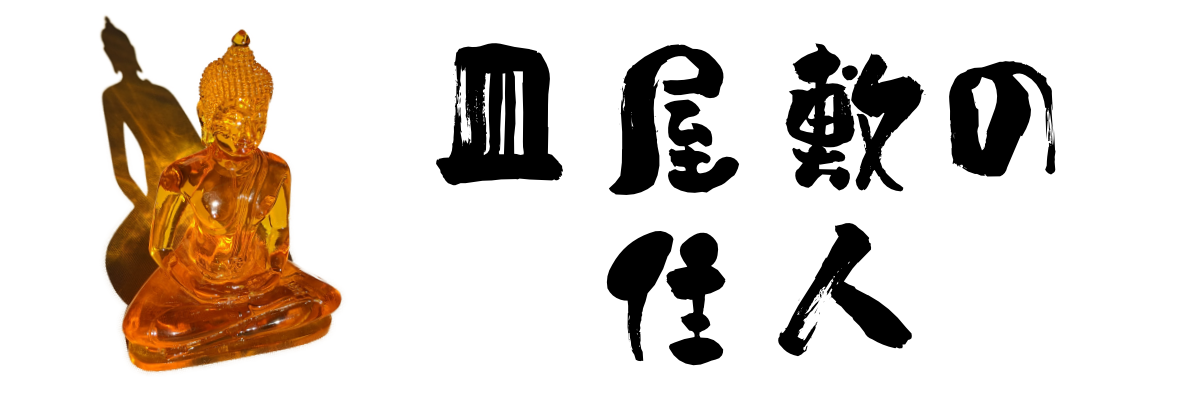こんにちは、アジアン食器専門店サラヤシキの藤井です。
毎年この季節にお馴染みの「梅仕事」ですが、2025年も無事に美味しい梅干しを完成させることができました。
梅干しの作り方については「梅干し 作り方」で検索するとプロの方の詳しいレシピが沢山出てくる(便利な時代になりました)ので、今回は割愛させていただきます。
私が住んでいる奈良県大和高田市では、大体5月下旬~6月上旬にかけて青梅が店頭に並びはじめますが、私はいつも出始めの購入は避けて2週間ほど様子を見ることにしています。個人の所感ですが、出始めは少し価格が高めに設定されていて、しばらく待つことで価格が落ち着いてくるからです。
今年は1キロ700円の完熟梅を2袋買いました。
【注意】梅酒やシロップ作りに使用するのは青梅、梅干しには表面が黄色くなった完熟梅を使用します。お間違えないように!
ヘタを取ったり焼酎をかけて消毒したりと下ごしらえをしている段階から家の中がフルーティーな香りに包まれ、これは「当たり」だと早くも確信しました。

さすがに3回目となると手慣れたものです。
竹串でヘタを取り、カビ防止のため焼酎をくぐらせた完熟梅を食塩と交互に入れていきます。最後に重しを乗せるのですが、容器の入口が狭いので私の場合はビニール袋に水を入れたものをいくつか乗せます。万が一袋に穴が開くと台無しになるのであまりお勧めではありませんが、幸い今まで失敗した経験はありません。

それから僅か数日で梅酢が溢れてきます。塩しか入れていないのにこれだけの水分が出てくるのが不思議ですね。
去年ははちみつ梅にしましたが、今回は王道のしそ梅にしようということで、赤しその葉っぱを予め塩もみし、あく抜きしたものを投入しました。しその葉の下ごしらえは途方もなく面倒な作業ですが、今年は頑張りました!

それから毎日瓶の中の様子を確認しながら2週間ほど放置し、晴れた日に天日干しすれば完成!
「梅雨明けの晴れ予報が続くタイミングを見計らって三日三晩干す」と言うのが昔からのセオリーのようですが、昨今の猛暑では二日くらいがベストだと思っています。あまり干しすぎると果肉が痩せてカラカラになってしまうので、表面が乾いた程よいミディアムレアを見極めることが大事です。
今年は完熟梅の段階で色艶が良く香りも強かったので、自分史上最高の出来になることは確信していました。写真は一切加工していませんが、それでもこの赤さ!大満足の完成度です。

こちらが完成品。一緒に干したしその葉はフードプロセッサーで粉々にすれば自家製のゆかりになります。白ご飯が大好きな私にとっては最高の瞬間です!

今回梅干し入れに使用したにはこちら!タイの定番食器「ブルー&ホワイト」のパイナップルボウル壺型です。ぷっくりとした可愛いらしい形状が魅力です。

自家製ゆかり入れに使用したのは同シリーズのミニポットです。小さなスプーンがついている調味料入れに最適です。こちらは7月現在欠品中ですが、8月上旬には入荷予定です。気になった方は是非チェックを!入荷情報はサラヤシキのInstagramでも随時配信しています。